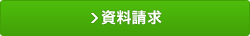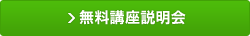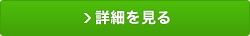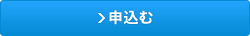TACのズバリ的中!
毎年多くの的中実績!これぞTAC教材の精度の証明
TACは本試験の出題傾向を徹底的に分析して、答練・模試などの問題作成を行っています。
その長年のノウハウにより蓄積されたデータと、緻密な分析により、
毎年多くの「本試験ズバリ的中」を出しています。
これはTACが提供するアウトプット教材の精度が高いことを物語っています。
これだけズバリ的中を続出させることも多数の合格者輩出への原動力です。
下記はほんの一例です。もちろん他にも多数の「ズバリ的中」を実現しています!
憲 法
| 2024年合格目標 TAC教材 | 令和6年度 行政書士本試験問題 |
|---|---|
| 総合答練②憲法【問題3】肢1…○ 氏名は、その個人の人格の象徴であって、人格権の一内容を構成するものであるが、婚姻および家族に関する法制度の一部として法律がその具体的な内容を規律しているものであるから、具体的な法制度を離れて、氏が変更されること自体を捉えて直ちに人格権を侵害し、違憲であるか否かを論ずることは相当ではない。 |
本試験問題憲法【問題3】肢1…○ 氏名は、社会的にみれば、個人を他人から識別し特定する機能を有するものであるが、同時に、その個人からみれば、人が個人として尊重される基礎であり、その個人の人格の象徴であって、人格権の一内容を構成する。 |
| 総合答練②憲法【問題3】肢2…○ 家族は社会の自然かつ基礎的な集団単位であるから、個人の呼称の一部である氏をその個人の属する集団を想起させるものとして一つに定めることにも合理性があるといえる。 |
本試験問題憲法【問題3】肢3…○ 家族は社会の自然かつ基礎的な集団単位であるから、氏をその個人の属する集団を想起させるものとして一つに定めることにも合理性があり、また氏が身分関係の変動に伴って改められることがあり得ることは、その性質上予定されている。 |
| スーパー答練1st憲法①【問題12】…空欄ア(家族) … [ ア ] は社会の自然かつ基礎的な集団単位と捉えられ、その呼称を一つに定めることには合理性が認められる。… |
本試験問題憲法【問題3】肢3…○
|
| 全国公開模試②憲法【問題4】肢ウ…× 検索事業者は、インターネット上のウェブサイトに掲載されている情報を網羅的に収集してその複製を保存し、同複製を基にした索引を作成するなどして情報を整理し、利用者から示された一定の条件に対応する情報を同索引に基づいて検索結果として提供するものであるが、この情報の収集、整理および提供はプログラムにより自動的に行われるものであるから、検索結果の提供は検索事業者自身による表現行為という側面を有するとはいえない。 |
本試験問題憲法【問題4】肢2…×
|
| スーパー答練1st憲法②【問題15】肢エ…○ 憲法上、「義務教育は、これを無償とする。」と定められているが、判例は、これは義務教育の対価である授業料を徴収しないことを意味するものと判断している。 |
本試験問題憲法【問題5】肢1…○
|
| スーパー答練2nd憲法【問題9】肢エ…× 憲法の義務教育は無償とするとの規定は、授業料の他に、教科書、学用品その他教育に必要な一切の費用まで無償としなければならないことを定めたものである。 |
本試験問題憲法【問題5】肢1…○
|
|
総合答練③憲法【問題5】肢2…○ 憲法26条の規定の背後には、国民各自が、一個の人間として、また、一市民として、成長、発達し、自己の人格を完成、実現するために必要な学習をする固有の権利を有すること、特に、みずから学習することのできない子どもは、その学習要求を充足するための教育を自己に施すことを大人一般に対して要求する権利を有するとの観念が存在している。 |
本試験問題憲法【問題5】肢4…○
|
| ミニテスト憲法⑤【問題2】肢3…× みずから学習することのできない子どもは、その学習要求を充足するための教育を自己に施すことを大人一般に対して要求する権利を有しない。 |
本試験問題憲法【問題5】肢4…○ 国民の教育を受ける権利を定める憲法規定の背後には、みずから学習することのできない子どもは、その学習要求を充足するための教育を自己に施すことを大人一般に対して要求する権利を有するとの観念が存在している。 |
| 総合答練③憲法【問題5】肢3…○ 普通教育においては、児童生徒に教授内容を批判する能力がなく、教師が児童生徒に対して強い影響力、支配力を有するほか、子どもの側に学校や教師を選択する余地が乏しく、教育の機会均等をはかる上からも全国的に一定の水準を確保すべき強い要請があること等からすれば、普通教育における教師に完全な教授の自由を認めることはできない。 |
本試験問題憲法【問題5】肢5…〇 普通教育では、児童生徒に十分な批判能力がなく、また、全国的に一定の教育水準を確保すべき強い要請があること等からすれば、教師に完全な教授の自由を認めることはとうてい許されない。 |
|
スーパー答練1st憲法②【問題13】肢2…○ 大学教育の場合には、学生が一応教授内容を批判する能力を備えていると考えられるのに対し、普通教育においては、児童生徒にこのような能力がないこと等に思いをいたすときは、普通教育における教師に完全な教授の自由を認めることは、とうてい許されない。 |
本試験問題憲法【問題5】肢5…〇 普通教育では、児童生徒に十分な批判能力がなく、また、全国的に一定の教育水準を確保すべき強い要請があること等からすれば、教師に完全な教授の自由を認めることはとうてい許されない。 |
|
スーパー答練2nd憲法【問題6】肢3…○ |
本試験問題憲法【問題5】肢5…〇
学問の自由は、学問研究の自由だけでなく、その結果を教授する自由も含むが、大学教育の場合と異なり、普通教育においては、教師に完全な教授の自由を認めることは許されない。 |
|
総合答練①憲法【問題5】肢3…○ 選挙制度の仕組みを具体的に決定することは国会の広い裁量にゆだねられているところ、同時に行われる二つの選挙に同一の候補者が重複して立候補することを認めるか否かは、選挙制度の仕組みの一つとして、国会が裁量により決定することができる事項であるといわざるを得ない。 |
本試験問題憲法【問題6】肢3…〇
|
|
スーパー答練1st憲法②【問題8】肢4…○ 名簿式比例代表制は、政党の選択という意味を持たない投票を認めない制度であるから、非拘束名簿式比例代表制の下においても、名簿登載者個人には投票したいが、その者の所属する政党等には投票したくないという投票意思が認められないからといって憲法に違反するとはいえない。 |
本試験問題憲法【問題6】肢4…○
|
|
スーパー答練1st憲法②【問題19】肢5…× 両議院の議員には、不逮捕特権が認められるが、緊急集会中の期間は国会の会期ではないので、その期間中の参議院の議員については、その特権は及ばない。 |
本試験問題憲法【問題7】肢4…○
|
民 法
| 2024年合格目標 TAC教材 | 令和6年度 行政書士本試験問題 |
|---|---|
| 科目別答練民法①【問題1】肢5…× Aについて失踪宣告がされ、Aが死亡したものとみなされた後にAの生存が判明した場合、失踪宣告によって権利能力がはく奪された以上、失踪宣告がされた後にAがした売買契約は、失踪宣告が取り消されなければ有効とはならない。 |
本試験問題民法【問題27】肢2…× 失踪の宣告を受けた者が実際には生存しており、不法行為により身体的被害を受けていたとしても、失踪の宣告が取り消されなければ、損害賠償請求権は発生しない。 |
| スーパー答練2nd民法①【問題4】肢ウ…○ (Aが夫Bにつき失踪宣告を受けた場合)Aは、Bを相続したことにより取得したB所有の土地をCに譲渡した後に、Bが生存していることが判明し、失踪宣告が取り消された。AがBの生存を知っている場合には、Cが知らなかったとしても、Bは、Cに対して、その土地の返還を請求することができる。 |
本試験問題民法【問題27】肢5…× 失踪の宣告によって失踪者の所有する甲土地を相続した者が、甲土地を第三者に売却した後に、失踪者の生存が判明し、この者の失踪の宣告が取り消された。この場合において、相続人が失踪者の生存について善意であったときは、第三者が悪意であっても、甲土地の売買契約による所有権移転の効果に影響しない。 |
| 総合答練②民法【問題27】肢5…× (未成年者をA、その法定代理人をBとするとき、)Aが、Bの同意を得ないで法律行為をした場合には、Bだけでなく、A自身も当該法律行為を取り消すことができるが、その場合には、Bの同意を得て行わなければならない。 |
本試験問題民法【問題28】肢4…○ 未成年者が親権者の同意を得ずに締結した契約について、未成年者本人が、制限行為能力を理由としてこれを取り消す場合、親権者の同意を得る必要はない。 |
| 総合答練①民法【問題29】肢ウ…× Aが死亡し、相続人である妻Bと子CがA所有の甲土地を共同相続したが、Bは、勝手に単独で所有権を取得した旨の登記をした後、甲土地をDに譲渡し、Dが甲土地の単独の所有権移転登記を備えた場合、Cは登記なくして、自己の持分をDに対抗することはできない。 |
本試験問題民法【問題29】肢1…○ (甲土地(以下「甲」という。)を所有するAが死亡して、その子であるBおよびCについて相続が開始した。)遺産分割が終了していないにもかかわらず、甲につきBが虚偽の登記申請に基づいて単独所有名義で相続登記手続を行った上で、これをDに売却して所有権移転登記手続が行われた場合、Cは、Dに対して、Cの法定相続分に基づく持分権を登記なくして主張することができる。 |
| 総合答練①民法【問題29】肢エ…○ Aが死亡し、相続人である妻Bと子CがA所有の甲土地を共同相続したが、BC間でBが甲土地の単独所有権を取得する旨の遺産分割がされた後、Cが自己の法定相続分に応じた持分をDに譲渡した場合、Bは登記を経なければ、遺産分割後に甲土地について権利を取得したDに対して、自己の権利の取得を対抗することはできない。 |
本試験問題民法【問題29】肢2…○ (甲土地(以下「甲」という。)を所有するAが死亡して、その子であるBおよびCについて相続が開始した。)遺産分割により甲をCが単独で相続することとなったが、Cが相続登記手続をしないうちに、Bが甲に関する自己の法定相続分に基づく持分権につき相続登記手続を行った上で、これをEに売却して持分権移転登記手続が行われた場合、Cは、Eに対して、Eの持分権が自己に帰属する旨を主張することができない。 |
| 科目別答練民法①【問題12】肢5…○ AB間の遺産分割協議によりAが甲不動産の単独所有権を取得することとされた後、Bの債権者CがBの法定相続分に応じた持分を差し押えた場合、Aは、Cに対して、登記を備えなければ、甲不動産の単独所有権の取得を対抗することができない。 |
本試験問題民法【問題29】肢2…○ (甲土地(以下「甲」という。)を所有するAが死亡して、その子であるBおよびCについて相続が開始した。)遺産分割により甲をCが単独で相続することとなったが、Cが相続登記手続をしないうちに、Bが甲に関する自己の法定相続分に基づく持分権につき相続登記手続を行った上で、これをEに売却して持分権移転登記手続が行われた場合、Cは、Eに対して、Eの持分権が自己に帰属する旨を主張することができない。 |
| スーパー答練1st民法②【問題2】肢1…○ 共同相続人の一人であるAが、遺産分割により、法定相続分を超えて甲土地の全部の所有権を取得したが、その登記をしていなかった。他の共同相続人Bの債権者であるCが、分割前のBの法定相続分について甲土地を差し押さえ、その登記をしたときは、Aは、Cに対して分割により甲土地の全部の所有権を取得したことを対抗することができない。 |
本試験問題民法【問題29】肢2…○ (甲土地(以下「甲」という。)を所有するAが死亡して、その子であるBおよびCについて相続が開始した。)遺産分割により甲をCが単独で相続することとなったが、Cが相続登記手続をしないうちに、Bが甲に関する自己の法定相続分に基づく持分権につき相続登記手続を行った上で、これをEに売却して持分権移転登記手続が行われた場合、Cは、Eに対して、Eの持分権が自己に帰属する旨を主張することができない。 |
| 総合答練①民法【問題29】肢オ…× Aが死亡し、相続人として妻Bと子Cがいたが、Bが相続放棄をし、相続財産である甲土地はCの単独所有となった。しかし、その後、Bの債権者DがBに代位して共同相続の登記をし、Bの持分を差し押さえた場合、Cは登記なくして、甲土地の単独所有権をDに対抗することはできない。 |
本試験問題民法【問題29】肢4…× (甲土地(以下「甲」という。)を所有するAが死亡して、その子であるBおよびCについて相続が開始した。)Bが相続を放棄したため、甲はCが単独で相続することとなったが、Cが相続登記手続をしないうちに、Bの債権者であるGが甲に関するBの法定相続分に基づく持分権につき差押えを申し立てた場合、Cは、当該差押えの無効を主張することができない。 |
| 科目別答練民法①【問題12】肢4…× Aが死亡し、BとCがA所有の甲不動産を共同相続したが、このうちBが相続を放棄した後、Bの債権者であるDがBに代位して共同相続の登記をし、Bの持分を差し押さえた場合、Cは、登記をしなければ、Dに対して自己が甲不動産の単独の所有者であることを対抗することができない。 |
本試験問題民法【問題29】肢4…× (甲土地(以下「甲」という。)を所有するAが死亡して、その子であるBおよびCについて相続が開始した。)Bが相続を放棄したため、甲はCが単独で相続することとなったが、Cが相続登記手続をしないうちに、Bの債権者であるGが甲に関するBの法定相続分に基づく持分権につき差押えを申し立てた場合、Cは、当該差押えの無効を主張することができない。 |
| スーパー答練2nd民法①【問題14】肢1…× 甲土地の共同相続人であるAとBのうち、Aが相続を放棄した後、Aの債権者であるCがAに代位して共同相続の登記をし、Aの持分を差し押さえた場合、Bは、登記をしなければ、Cに対して自己が甲土地の単独の所有者であることを対抗することができない。 |
本試験問題民法【問題29】肢4…× (甲土地(以下「甲」という。)を所有するAが死亡して、その子であるBおよびCについて相続が開始した。)Bが相続を放棄したため、甲はCが単独で相続することとなったが、Cが相続登記手続をしないうちに、Bの債権者であるGが甲に関するBの法定相続分に基づく持分権につき差押えを申し立てた場合、Cは、当該差押えの無効を主張することができない。 |
| 総合答練②民法【問題30】肢ア…× (AはBに1000万円を貸し付け、この貸金債権を担保するためにB所有の甲土地に抵当権を設定し、登記も備えた。)抵当権設定登記後にBが甲土地をCに賃貸してCがその旨の登記を備えた場合、抵当権実行による買受人Dからの明渡請求に対して、賃借人Cは、明渡しまでの使用の対価を支払うことなく、6か月の明渡猶予期間を与えられる。 |
本試験問題民法【問題30】肢2…× (Aが所有する甲建物(以下「甲」という。)につき、Bのために抵当権が設定されて抵当権設定登記が行われた後、Cのために賃借権が設定され、Cは使用収益を開始した。)Bの抵当権が実行された場合において、買受人Dは、Cに対して、直ちに所有権に基づく妨害排除請求として甲の明渡しを求めることができる。 |
| 科目別答練民法①【問題18】肢4…× (AがBに対して有する債権を担保するために、B所有の不動産に抵当権の設定を受けてその旨の登記を備えた場合)AがB所有の乙建物に抵当権の設定を受けて、その旨の登記を備えた後、Bは、乙建物をCに賃貸し引き渡した場合、BがCに対する賃料債権をDに譲渡し、この譲渡についてBからCに対して確定日付のある証書によって通知がなされたときは、Aは、物上代位権を行使して、この賃料債権を差し押さえることはできない。 |
本試験問題民法【問題30】肢3…○ (Aが所有する甲建物(以下「甲」という。)につき、Bのために抵当権が設定されて抵当権設定登記が行われた後、Cのために賃借権が設定され、Cは使用収益を開始した。)AがCに対して有する賃料債権をEに譲渡し、その旨の債権譲渡通知が内容証明郵便によって行われた後、Bが抵当権に基づく物上代位権の行使として当該賃料債権に対して差押えを行った場合、当該賃料債権につきCがいまだEに弁済していないときは、Cは、Bの賃料支払請求を拒むことができない。 |
| スーパー答練1st民法②【問題16】肢ウ…○ (Aは、Bに対する貸金債務を担保するために自己所有の建物に抵当権を設定し、その旨の登記をした。その後、Aは、この建物をCに賃貸し、Cは、Aに敷金を交付した。)AがCに対する賃料債権をEに譲渡し、この譲渡についてAからCに対して確定日付のある証書によって通知がなされたとしても、Bは、原則として、物上代位権を行使して、この賃料債権を差し押さえることができる。 |
本試験問題民法【問題30】肢3…○ (Aが所有する甲建物(以下「甲」という。)につき、Bのために抵当権が設定されて抵当権設定登記が行われた後、Cのために賃借権が設定され、Cは使用収益を開始した。)AがCに対して有する賃料債権をEに譲渡し、その旨の債権譲渡通知が内容証明郵便によって行われた後、Bが抵当権に基づく物上代位権の行使として当該賃料債権に対して差押えを行った場合、当該賃料債権につきCがいまだEに弁済していないときは、Cは、Bの賃料支払請求を拒むことができない。 |
| スーパー答練2nd民法②【問題7】肢3…○ (Aが、Bに対する貸金債務を担保するために、自己所有の甲不動産に抵当権を設定し、その旨の登記をした場合)Aが競売手続を妨害する目的で、甲不動産をCに賃貸した結果、甲不動産の交換価値の実現が妨げられBの優先弁済請求権の行使が困難となった。この場合、Bは、抵当権に基づく妨害排除請求権を行使することができるが、Aが甲不動産を適切に維持管理することが期待できないときは、Cに対して、直接自己に甲不動産の明渡しを請求することができる。 |
本試験問題民法【問題30】肢4…× (Aが所有する甲建物(以下「甲」という。)につき、Bのために抵当権が設定されて抵当権設定登記が行われた後、Cのために賃借権が設定され、Cは使用収益を開始した。)Cのための賃借権の設定においてBの抵当権の実行を妨害する目的が認められ、Cの占有により甲の交換価値の実現が妨げられてBの優先弁済権の行使が困難となるような状態がある場合、Aにおいて抵当権に対する侵害が生じないように甲を適切に維持管理することが期待できるときであっても、Bは、Cに対して、抵当権に基づく妨害排除請求として甲の直接自己への明渡しを求めることができる。 |
| 総合答練②民法【問題30】肢ウ…○ Bは、Aから金銭を借り入れ、その返還債務の担保のために自己所有の建物に抵当権を設定し、同建物をCに賃貸していたところ、Cは自ら居住せず、Bの承諾を得て同建物をDに転貸していた場合、Aは、原則として、CがDに対して有する賃料債権に抵当権の効力を及ぼすことはできない。 |
本試験問題民法【問題30】肢5…× (Aが所有する甲建物(以下「甲」という。)につき、Bのために抵当権が設定されて抵当権設定登記が行われた後、Cのために賃借権が設定され、Cは使用収益を開始した。)CがAの承諾を得て甲をFに転貸借した場合、Bは、特段の事情がない限り、CがFに対して有する転貸賃料債権につき、物上代位権を行使することができる。 |
| 科目別答練民法①【問題18】肢5…× (AがBに対して有する債権を担保するために、B所有の不動産に抵当権の設定を受けてその旨の登記を備えた場合)AがB所有の乙建物に抵当権の設定を受けて、その旨の登記を備えた後、Bは、乙建物をCに賃貸し引き渡した上で、さらにCがDに対して乙建物を転貸し引き渡した場合、原則として、Aは、物上代位権を行使して、CのDに対する転貸賃料債権を差し押さえることができる。 |
本試験問題民法【問題30】肢5…× (Aが所有する甲建物(以下「甲」という。)につき、Bのために抵当権が設定されて抵当権設定登記が行われた後、Cのために賃借権が設定され、Cは使用収益を開始した。)CがAの承諾を得て甲をFに転貸借した場合、Bは、特段の事情がない限り、CがFに対して有する転貸賃料債権につき、物上代位権を行使することができる。 |
| スーパー答練1st民法②【問題19】肢イ…○ (AはBに対して貸金債権を有しており、この債権を被担保債権としてB所有の土地に抵当権の設定を受けた。)Bが土地をCに賃貸し、Cがこの土地をDに転貸した場合、Aは、原則として、物上代位権を行使してCが取得する転貸賃料債権を差し押さえることができない。 |
本試験問題民法【問題30】肢5…× (Aが所有する甲建物(以下「甲」という。)につき、Bのために抵当権が設定されて抵当権設定登記が行われた後、Cのために賃借権が設定され、Cは使用収益を開始した。)CがAの承諾を得て甲をFに転貸借した場合、Bは、特段の事情がない限り、CがFに対して有する転貸賃料債権につき、物上代位権を行使することができる。 |
| スーパー答練2nd民法②【問題4】肢2…○ Bは、Aから金銭を借り入れ、その返還債務の担保のために自己所有の建物に抵当権を設定し、同建物をCに賃貸していたところ、Cは自ら居住せず、Bの承諾を得て同建物をDに転貸していた場合、Aは、原則として、CがDに対して有する賃料債権に抵当権の効力を及ぼすことはできない。 |
本試験問題民法【問題30】肢5…× (Aが所有する甲建物(以下「甲」という。)につき、Bのために抵当権が設定されて抵当権設定登記が行われた後、Cのために賃借権が設定され、Cは使用収益を開始した。)CがAの承諾を得て甲をFに転貸借した場合、Bは、特段の事情がない限り、CがFに対して有する転貸賃料債権につき、物上代位権を行使することができる。 |
| ミニテスト民法⑫【問題1】肢4…○ 債務者が保証人を立てる義務を負う場合、債権者が保証人を指名したときを除き、行為能力者であって、かつ、弁済をする資力を有する者を保証人に立てなければならない。 |
本試験問題民法【問題31】肢2…× (Aは、Bから金銭を借り受け、Cが、Aの同貸金債務を保証した。)AがBに対し保証人を立てる義務を負う場合において、BがCを指名するときは、Cは、行為能力者でなければならない。 |
| ミニテスト民法⑫【問題1】肢2…○ 保証人は、特約のない限り、主たる債務の元本のほか、利息、違約金、損害賠償その他主たる債務から生ずるすべてのものを弁済しなければならない。 |
本試験問題民法【問題31】肢4…○ (Aは、Bから金銭を借り受け、Cが、Aの同貸金債務を保証した。)Cの保証債務は、Aの債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのものを包含する。 |
| 総合答練①民法【問題32】肢2…○ (Aは、BのCに対する100万円の債務を担保するため、Cと保証契約を締結した。)BのCに対する債務の履行について違約金の約定がない場合においても、Aは、保証債務についてのみ、Cと違約金の約定をすることができる。 |
本試験問題民法【問題31】肢5…○ (Aは、Bから金銭を借り受け、Cが、Aの同貸金債務を保証した。)Cは、その保証債務についてのみ、違約金又は損害賠償の額を約定することができる。 |
| ミニテスト民法⑫【問題1】肢1…× 保証人は、保証債務についてのみ違約金・損害賠償の額を約定することはできない。 |
本試験問題民法【問題31】肢5…○ (Aは、Bから金銭を借り受け、Cが、Aの同貸金債務を保証した。)Cは、その保証債務についてのみ、違約金又は損害賠償の額を約定することができる。 |
| ミニテスト民法⑥【問題2】肢5…○ Aが無権代理人Bから物を購入した場合、Aは、即時取得により、その物の所有権を取得することはできない。 |
本試験問題民法【問題32】肢3…× (A所有の動産甲(以下「甲」という。)を、BがCに売却する契約(以下「本件契約」という。))Bが、B自身をAの代理人と偽って、Aを売主、Cを買主とする本件契約を締結し、Cに対して甲を現実に引き渡した場合、Cは即時取得により甲の所有権を取得する。 |
| スーパー答練1st民法②【問題5】肢5…× Aが無権代理人Bから物を購入した場合、Aはその物を即時取得できる可能性がある。 |
本試験問題民法【問題32】肢3…× (A所有の動産甲(以下「甲」という。)を、BがCに売却する契約(以下「本件契約」という。))Bが、B自身をAの代理人と偽って、Aを売主、Cを買主とする本件契約を締結し、Cに対して甲を現実に引き渡した場合、Cは即時取得により甲の所有権を取得する。 |
| スーパー答練2nd民法①【問題17】肢1…× Aの宝石を占有していた宝石商Bは、処分権限がないにもかかわらず、これをAの代理人と称してCに売却し、現実に引き渡した。その後、AがCに対して宝石の返還を請求した場合、Cは、Bに代理権があると過失なく信じ、かつ、平穏、公然と占有を開始していたならば、宝石の所有権を即時取得したことを理由に、Aの請求を拒むことができる。 |
本試験問題民法【問題32】肢3…× (A所有の動産甲(以下「甲」という。)を、BがCに売却する契約(以下「本件契約」という。))Bが、B自身をAの代理人と偽って、Aを売主、Cを買主とする本件契約を締結し、Cに対して甲を現実に引き渡した場合、Cは即時取得により甲の所有権を取得する。 |
| スーパー答練2nd民法③【問題12】肢イ…× 他人の居眠り運転によって姉が受傷しその後死亡した場合、その妹のみが相続人であったときには、姉の不法行為者に対する損害賠償請求権を相続によって取得することになるが、妹には固有の慰謝料請求権は認められることはない。 |
本試験問題民法【問題34】肢1…× 不法行為による生命侵害の場合において、被害者の相続人であれば、常に近親者固有の慰謝料請求権が認められる。 |
| スーパー答練1st民法⑤【問題7】肢イ…× A運送会社の代表者Ⅾが、Cの運転する自動車にひかれて受傷した。Aは、個人会社であり実権がⅮに集中し、ⅮにAの機関としての代替性がなく、経済的にAとⅮとが一体をなす関係にあったとしても、AとDは法律上別人格であるため、Ⅾの受傷によりAの被った損害の賠償をCに請求することはできない。 |
本試験問題民法【問題34】肢3…○ 交通事故による被害者が、いわゆる個人会社の唯一の代表取締役であり、被害者には当該会社の機関としての代替性がなく、被害者と当該会社とが経済的に一体をなす等の事情の下では、当該会社は、加害者に対し、被害者の負傷のため営業利益を逸失したことによる賠償を請求することができる。 |
行政法
| 2024年合格目標 TAC教材 | 令和6年度 行政書士本試験問題 |
|---|---|
| ミニテスト行政法②【問題4】肢5…× 先行行為に瑕疵があり、先行行為と後行行為が相互に関連する場合には、それぞれが別個の目的を指向し、相互の間に手段目的の関係がなくても、先行行為の違法性は必ず後行行為に承継される。 |
本試験問題行政法【問題8】肢4…× 処分Aの違法がこれに後続する処分Bに承継されることが認められる場合であっても、処分Aの取消訴訟の出訴期間が経過している場合には、処分Bの取消訴訟において処分Aの違法を主張することは許されない。 |
| スーパー答練1st憲法③【問題2】肢5…○ 内閣は、憲法および法律の規定を実施するために政令を制定することができるが、この政令には、特にその法律の委任がある場合には、罰則を設けることができる。 |
本試験問題行政法【問題9】肢2…○ 法律の規定を実施するために政令を定めるのは内閣の事務であるが、その法律による委任がある場合には、政令に罰則を設けることもできる。 |
| ミニテスト行政法①【問題5】空欄A(信義則)、B(納税者間の平等、公平)、C(正義) 法の一般原理である [ A ] の法理の適用により、右課税処分を違法なものとして取り消すことができる場合があるとしても、法律による行政の原理なかんずく租税法律主義の原則が貫かれるべき租税法律関係においては、右法理の適用については慎重でなければならず、租税法規の適用における [ B ] という要請を犠牲にしてもなお当該課税処分に係る課税を免れしめて納税者の信頼を保護しなければ [ C ] に反するといえるような特別の事情が存する場合に、初めて右法理の適用の是非を考えるべきものである。 |
本試験問題行政法【問題10】肢3…× 法の一般原則である信義則の法理は、行政法関係においても一般に適用されるものであるとはいえ、租税法律主義の原則が貫かれるべき租税法律関係においては、租税法規に適合する課税処分について信義則の法理の適用により当該課税処分を違法なものとして取り消すことは、争われた事案の個別の状況や特段の事情の有無にかかわらず、租税法律主義に反するものとして認められない。 |
| スーパー答練2nd行政法①【問題2】肢エ…○ 租税法規に適合する課税処分については、租税法律主義の原則が貫かれるべき租税関係に関するものであるから、納税者間の平等、公平という要請を犠牲にしてもなお納税者の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別の事情が存する場合に初めて信義則の法理の適用の是非を考えるべきである。 |
本試験問題行政法【問題10】肢3…× 法の一般原則である信義則の法理は、行政法関係においても一般に適用されるものであるとはいえ、租税法律主義の原則が貫かれるべき租税法律関係においては、租税法規に適合する課税処分について信義則の法理の適用により当該課税処分を違法なものとして取り消すことは、争われた事案の個別の状況や特段の事情の有無にかかわらず、租税法律主義に反するものとして認められない。 |
| スーパー答練1st行政法①(多肢選択式)【問題1】空欄エ(不法行為) 右施策が変更されることにより、前記の勧告等に動機づけられて前記のような活動に入った者がその信頼に反して所期の活動を妨げられ、社会観念上看過することのできない程度の積極的損害を被る場合に、地方公共団体において右損害を補償するなどの代償的措置を講ずることなく施策を変更することは、それがやむをえない客観的事情によるのでない限り、当事者間に形成された信頼関係を不当に破壊するものとして違法性を帯び、地方公共団体の [ エ ] 責任を生ぜしめるものといわなければならない。 |
本試験問題行政法【問題10】肢4…○ 地方公共団体が将来にわたって継続すべき施策を決定した場合でも、当該施策が社会情勢の変動等に伴って変更されることがあることは当然であるが、当該地方公共団体の勧告ないし勧誘に動機付けられて施策の継続を前提とした活動に入った者が社会観念上看過することのできない程度の積極的損害を被る場合において、地方公共団体が当該損害を補償するなどの措置を講ずることなく施策を変更することは、それがやむをえない客観的事情によるのでない限り、当事者間に形成された信頼関係を不当に破壊するものとして違法となる。 |
| スーパー答練2nd行政法①【問題2】肢ア…× 普通地方公共団体が、違法な通達に基づき健康管理手当の支給を打ち切る措置をしたとしても、当該通達に基づき不支給を決定した以上は、当該支給を打ち切られた受給権者の権利不行使を理由として消滅時効の主張をすることは、信義則に反しない。 |
本試験問題行政法【問題10】肢5…× 国の通達に基づいて、地方公共団体が被爆者援護法等に基づく健康管理手当の支給を打ち切った後、当該通達が法律の解釈を誤ったものであるとして廃止された場合であっても、行政機関は通達に従い法律を執行する義務があることからすれば、廃止前の通達に基づいて打ち切られていた手当の支払いを求める訴訟において、地方公共団体が消滅時効を主張することは信義則に反しない。 |
| スーパー答練1st行政法②【問題8】肢1…○ 申請により求められた許認可等を拒否する処分その他申請に基づき当該申請をした者を名あて人としてされる処分は、行政手続法上の不利益処分に該当しない。 |
本試験問題行政法【問題11】肢4…× 本件処分は、申請に対する処分を取り消すものであるので、本件処分をするに際して、行政庁は許認可等の性質に照らしてできる限り具体的な審査基準を定めなければならない。 |
| 全国公開模試②【問題12】肢4…× 法令上必要とされる資格がなかったことまたは失われるに至ったことが判明した場合に必ずすることとされている不利益処分であって、その資格の不存在または喪失の事実が裁判所の判決書または決定書、一定の職に就いたことを証する当該任命権者の書類その他の客観的な資料により直接証明されたものをしようとするときであっても、聴聞手続をとらなければならない。 |
本試験問題行政法【問題11】肢5…○ 本件処分は、法令上必要とされる資格が失われるに至ったことが判明した場合に必ずすることとされている処分であり、その喪失の事実が客観的な資料により直接証明されるものであるので、行政庁は聴聞の手続をとる必要はない。 |
| 科目別答練行政法①【問題12】肢2…× 行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、行政機関が許認可等をする権限または許認可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、当該権限を行使し得る根拠となる法令の条項、その法令の条項に規定する要件、当該権限の行使がその法令の条項に規定する要件に適合する理由を示すよう努めなければならない。 |
本試験問題行政法【問題12】肢ア…○ 行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、行政機関が許認可等をする権限を行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、当該権限を行使し得る根拠となる法令の条項等、行政手続法が定める事項を示さなければならない。 |
| 総合答練②行政法【問題11】肢1…× 地方公共団体の機関がする行政指導であっても、その根拠となる規定が法令に置かれているものについては、行政手続法の行政指導に関する規定が適用される。 |
本試験問題行政法【問題12】肢イ…× 地方公共団体の機関がする行政指導については、その根拠となる規定が法律で定められている場合に限り、行政指導に関する行政手続法の規定が適用される。 |
| 総合答練③行政法【問題13】肢1…× 法令に違反する行為の是正を求める行政指導で、その根拠となる規定が法律に置かれているものが当該法律に規定する要件に適合しないと思料するときは、何人も、当該行政指導をした行政機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができる。 |
本試験問題行政法【問題12】肢ウ…○ 法令に違反する行為の是正を求める行政指導で、その根拠となる規定が法律に置かれているものを受けた相手方は、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした行政機関に対し、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができる。 |
| 科目別答練行政法①【問題12】肢5…○ 法令に違反する行為の是正を求める行政指導で、その根拠となる規定が法律に置かれているものについては、その行政指導の相手方は、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした行政機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを原則として求めることができる。 |
本試験問題行政法【問題12】肢ウ…○ 法令に違反する行為の是正を求める行政指導で、その根拠となる規定が法律に置かれているものを受けた相手方は、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした行政機関に対し、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができる。 |
| 科目別答練行政法①【問題9】肢5…○ 「命令等」とは、内閣または行政機関が定める法律に基づく命令または規則、審査基準、処分基準および行政指導指針をいう。 |
本試験問題行政法【問題12】肢エ…× 意見公募手続の対象である命令等には、審査基準や処分基準など、処分をするかどうかを判断するための基準は含まれるが、行政指導に関する指針は含まれない。 |
| スーパー答練2nd行政法①【問題11】肢イ…○ 命令等とは、内閣または行政機関が定める法律に基づく命令または規則、審査基準、処分基準および行政指導指針をいう。 |
本試験問題行政法【問題12】肢エ…× 意見公募手続の対象である命令等には、審査基準や処分基準など、処分をするかどうかを判断するための基準は含まれるが、行政指導に関する指針は含まれない。 |
| スーパー答練3rd①【問題7】肢3…× 意見公募手続の対象となる命令等は、外部に対して法的拘束力を有するものに限られるから、審査基準、処分基準は含まれるが、行政指導指針は含まれない。 |
本試験問題行政法【問題12】肢エ…× 意見公募手続の対象である命令等には、審査基準や処分基準など、処分をするかどうかを判断するための基準は含まれるが、行政指導に関する指針は含まれない。 |
| 全国公開模試①行政法【問題12】肢4…× 行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間を定めるよう努めなければならず、これを定めたときには、これらの当該申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にするよう努めなければならない。 |
本試験問題行政法【問題13】肢4…× 審査基準を公にする方法としては、法令により申請の提出先とされている機関の事務所において備え付けることのみが認められており、その他の方法は許容されていない。 |
| ミニテスト行政法⑤【問題2】肢4…× 行政庁は、審査基準を定め、行政上特別の支障があるときを除き、法令により申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により審査基準を公にしておくよう努めなければならない。 |
本試験問題行政法【問題13】肢4…× 審査基準を公にする方法としては、法令により申請の提出先とされている機関の事務所において備え付けることのみが認められており、その他の方法は許容されていない。 |
| スーパー答練3rd②行政法【問題7】肢2…× 不利益処分をするに当たっては、行政庁は、必ず処分基準を定め、かつ、これを公にしなければならない。 |
本試験問題行政法【問題13】肢5…× 行政庁が処分基準を定めることは努力義務に過ぎないが、処分基準を定めた場合には、これを公にする法的義務を負う。 |
| スーパー答練1st行政法③【問題5】肢2…○ 多数人が共同して審査請求をする場合には、3人以内の総代を互選することができる。 |
本試験問題行政法【問題14】肢3…× 多数人が共同して審査請求をしようとする場合、1人の総代を選ばなければならない。 |
| ミニテスト行政法⑥【問題4】肢2…○ 審査請求人が死亡した場合、その相続人は、審査庁の許可を得ることなく審査請求人の地位を承継する。 |
本試験問題行政法【問題14】肢4…× 審査請求人本人が死亡した場合、当該審査請求人の地位は消滅することから、当該審査請求の目的である処分に係る権利が承継されるか否かにかかわらず、当該審査請求は当然に終了する。 |
| 科目別答練行政法①【問題14】肢3…× 法人でない社団または財団は、その代表者または管理人の定めがないものであっても、その名で審査請求をすることができる。 |
本試験問題行政法【問題14】肢5…○ 法人でない社団または財団であっても、代表者または管理人の定めがあるものは、当該社団または財団の名で審査請求をすることができる。 |
| スーパー答練1st行政法③【問題5】肢1…× 法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めがあるものは、その社団または財団の名で審査請求をしなければならない。 |
本試験問題行政法【問題14】肢5…○ 法人でない社団または財団であっても、代表者または管理人の定めがあるものは、当該社団または財団の名で審査請求をすることができる。 |
| スーパー答練1st行政法③【問題15】肢4…○ 行政不服審査法には、審査請求の裁決について、行政事件訴訟法が定める取消判決の拘束力のような関係行政庁を拘束する規定が設けられている。 |
本試験問題行政法【問題16】肢ウ…○ 行訴法は、判決の拘束力について、「処分又は裁決を取り消す判決は、その事件について、処分又は裁決をした行政庁その他の関係行政庁を拘束する。」と定めているのに対し、行審法は、裁決の拘束力について、「裁決は、関係行政庁を拘束する。」と定めている。 |
| スーパー答練1st行政法④【問題6】肢オ…× 罷免処分を受けた公務員が、当該罷免処分の取消訴訟を提起したが、その後、市議会議員に立候補した場合、公職選挙法によれば、公務員は公職の届出をしたときは、その届出の日に当該公務員の職を辞したものとみなされるため、法律上の利益は消滅する。 |
本試験問題行政法【問題17】肢1…× 公務員に対する免職処分の取消訴訟における訴えの利益は、免職処分を受けた公務員が公職の選挙に立候補した後は、給料請求権等の回復可能性があるか否かにかかわらず、消滅する。 |
| スーパー答練3rd③行政法【問題9】肢2…○ 公務員が免職処分の取消訴訟係属中に公職に立候補した場合、当該公務員は、違法な免職処分がなされなければ有するはずであった給料請求権その他の権利・利益を回復させる利益があるから、免職処分を取り消す利益を有する。 |
本試験問題行政法【問題17】肢1…× 公務員に対する免職処分の取消訴訟における訴えの利益は、免職処分を受けた公務員が公職の選挙に立候補した後は、給料請求権等の回復可能性があるか否かにかかわらず、消滅する。 |
| スーパー答練2nd行政法②【問題10】肢5…○ 保安林指定解除処分に対する取消訴訟の係属中に、代替施設の設置により洪水や渇水の危険が解消された場合、それらの危険防止のために保安林を存続させる必要がないので、その取消しを求める訴えの利益は消滅する。 |
本試験問題行政法【問題17】肢2…○ 保安林指定解除処分の取消訴訟における訴えの利益は、原告適格の基礎とされた個別具体的な利益侵害状況が代替施設の設置によって解消するに至った場合には、消滅する。 |
| スーパー答練3rd③行政法【問題9】肢1…○ 保安林指定解除処分に対する取消訴訟の係属中に、代替施設の設置により洪水や渇水の危険が解消された場合、それらの危険防止のために保安林を存続させる必要がないので、その取消しを求める訴えの利益は消滅する。 |
本試験問題行政法【問題17】肢2…○ 保安林指定解除処分の取消訴訟における訴えの利益は、原告適格の基礎とされた個別具体的な利益侵害状況が代替施設の設置によって解消するに至った場合には、消滅する。 |
| 総合答練①行政法【問題19】肢オ…× 公文書の非公開決定の取消訴訟において、当該請求に係る公文書が書証として提出された場合、当該公文書の非公開決定の取消しを求める訴えの利益は消滅する。 |
本試験問題行政法【問題17】肢3…× 公文書非公開決定処分の取消訴訟における訴えの利益は、公開請求の対象である公文書が当該取消訴訟において書証として提出された場合には、消滅する。 |
| スーパー答練1st行政法④【問題5】肢2…○ 公文書の非公開決定の取消訴訟において当該公文書が書証として提出された場合であっても、当該公文書の非公開決定の取消しを求める利益は失われない。 |
本試験問題行政法【問題17】肢3…× 公文書非公開決定処分の取消訴訟における訴えの利益は、公開請求の対象である公文書が当該取消訴訟において書証として提出された場合には、消滅する。 |
| スーパー答練3rd③行政法【問題9】肢3…× 公文書公開条例に基づき公開請求された公文書の非公開決定の取消訴訟において、当該公文書が書証として提出された場合には、当該公文書の非公開決定の取消しを求める訴えの利益は消滅する。 |
本試験問題行政法【問題17】肢3…× 公文書非公開決定処分の取消訴訟における訴えの利益は、公開請求の対象である公文書が当該取消訴訟において書証として提出された場合には、消滅する。 |
| 科目別答練行政法②【問題4】肢エ…× 自動車運転免許の効力停止処分を受けた者は、停止期間を経過し、かつ、当該処分の日から無違反・無処分で1年間を経過したときは、当該処分を理由に道路交通法上不利益を受けることはないとしても、当該処分の記載のある免許証を所持することにより警察官に当該処分の存した事実を覚知され、名誉、感情、信用等を損なう可能性が継続して存在するから、当該処分の取消しを求める訴えの利益は失われない。 |
本試験問題行政法【問題17】肢4…× 運転免許停止処分の取消訴訟における訴えの利益は、免許停止期間が経過した場合であっても、取消判決により原告の名誉・感情・信用等の回復可能性がある場合には、消滅しない。 |
| スーパー答練1st行政法④【問題6】肢エ…○ 自動車運転免許停止処分を受けた者は、当該停止期間を経過し、かつ処分後1年間を無違反・無処分で経過した場合には、その経過により処分の効果は一切消滅することになるため、本件処分の取消しによって回復すべき法律上の利益を有しない。 |
本試験問題行政法【問題17】肢4…× 運転免許停止処分の取消訴訟における訴えの利益は、免許停止期間が経過した場合であっても、取消判決により原告の名誉・感情・信用等の回復可能性がある場合には、消滅しない。 |
| 全国公開模試②行政法【問題17】肢ウ…○ 裁判所は、相当と認めるときは、終局判決前に、判決をもって、処分または裁決が違法であることを宣言することができる。 |
本試験問題行政法【問題18】肢ア…○ 裁判所は、相当と認めるときは、終局判決前に、判決をもって、処分が違法であることを宣言することができる。 |
| スーパー答練3rd③行政法【問題10】肢オ…○ 裁判所は、相当と認めるときは、終局判決前に、判決をもって、処分または裁決が違法であることを宣言することができる。 |
本試験問題行政法【問題18】肢ア…○ 裁判所は、相当と認めるときは、終局判決前に、判決をもって、処分が違法であることを宣言することができる。 |
| 総合答練②行政法【問題19】肢2…× 処分または裁決を取り消す判決により権利を害された第三者で、訴訟に参加することができなかったため判決に影響を及ぼすべき攻撃または防御の方法を提出することができなかったものは、帰責事由の有無にかかわらず、確定の終局判決に対し、再審の訴えをもって、不服の申立てをすることができる。 |
本試験問題行政法【問題18】肢ウ…○ 処分または裁決を取り消す判決により権利を害された第三者で、自己の責めに帰することができない理由により訴訟に参加することができなかったため判決に影響を及ぼすべき攻撃または防御の方法を提出することができなかったものは、これを理由として、確定の終局判決に対し、再審の訴えをもって、不服の申立てをすることができる。 |
| スーパー答練2nd行政法②【問題15】肢5…○ 処分または裁決を取り消す判決により権利を害された第三者で、自己の責めに帰することができない理由により訴訟に参加することができなかったため判決に影響を及ぼすべき攻撃または防御の方法を提出することができなかったものは、これを理由として、確定の終局判決に対し、再審の訴えをもって、不服の申立てをすることができる。 |
本試験問題行政法【問題18】肢ウ…○ 処分または裁決を取り消す判決により権利を害された第三者で、自己の責めに帰することができない理由により訴訟に参加することができなかったため判決に影響を及ぼすべき攻撃または防御の方法を提出することができなかったものは、これを理由として、確定の終局判決に対し、再審の訴えをもって、不服の申立てをすることができる。 |
| スーパー答練1st行政法④【問題13】肢4…× 行政庁が一定の処分をすべきであるにかかわらずこれをしないときに行政庁に対して一定の処分をすべき旨を命ずることを求める訴訟を提起した場合、行政庁がその処分をすべきことがその処分の根拠となる法令の規定から明らかであると認められないときは、裁判所は、行政庁がその処分をすべき旨を命ずる判決をすることができない。 |
本試験問題行政法【問題18】肢エ…○ 直接型(非申請型)義務付け訴訟において、その訴訟要件がすべて満たされ、かつ当該訴えに係る処分について行政庁がこれをしないことが違法である場合には、裁判所は、行政庁がその処分をすべき旨を命じる判決をする。 |
| スーパー答練2nd行政法②【問題15】肢3…× 処分または裁決を取り消す判決は、その事件について、処分または裁決をした行政庁その他の関係行政庁を拘束するが、この規定は、取消訴訟以外の抗告訴訟については準用されていない。 |
本試験問題行政法【問題18】肢オ…× 処分を取り消す判決は、その事件について処分をした行政庁その他の関係行政庁を拘束すると規定されているが、この規定は、取消訴訟以外の抗告訴訟には準用されない。 |
| スーパー答練2nd行政法③【問題1】肢5…× 国の公権力の行使に当たる公務員が、その職務を行うについて、故意または重過失によって違法に他人に損害を生じさせた場合には、国だけでなく当該公務員も被害者に対して直接に責任を負う。 |
本試験問題行政法【問題21】肢2…× 公権力の行使に当たる国または公共団体の公務員が、その職務を行うについて、過失によって違法に他人に損害を加えた場合には、国または公共団体がその被害者に対して賠償責任を負うが、故意または重過失の場合には、公務員個人が被害者に対して直接に賠償責任を負う。 |
| 総合答練③行政法【問題21】肢1…○ 公務員が客観的に職務執行の外形をそなえる行為によって、他人に損害を加えた場合、当該公務員が自己の利益をはかる意図をもってする場合であっても、国家賠償責任を負う。 |
本試験問題行政法【問題21】肢4…× 国家賠償法1条1項が定める「公務員が、その職務を行うについて」という要件につき、公務員が主観的に権限行使の意思をもってするものではなく、専ら自己の利をはかる意図をもってするような場合には、たとえ客観的に職務執行の外形をそなえる行為をした場合であったとしても、この要件には該当しない。 |
| スーパー答練1st行政法⑤【問題2】肢エ…○ 公務員が客観的に職務執行の外形を備える行為をしこれによって他人に損害を加えた場合には、自己の利益を図る意図をもってその行為をしたにすぎないときであっても、国または公共団体は損害賠償責任を負う。 |
本試験問題行政法【問題21】肢4…× 国家賠償法1条1項が定める「公務員が、その職務を行うについて」という要件につき、公務員が主観的に権限行使の意思をもってするものではなく、専ら自己の利をはかる意図をもってするような場合には、たとえ客観的に職務執行の外形をそなえる行為をした場合であったとしても、この要件には該当しない。 |
| スーパー答練1st行政法⑤【問題2】肢ア…× 都道府県警察の警察官が交通犯罪の捜査を行うについて違法に他人に損害を加えた場合、国家賠償法1条1項により賠償責任を負うのは、国であって当該都道府県ではない。 |
本試験問題行政法【問題21】肢5…× 都道府県警察の警察官が、交通犯罪の捜査を行うにつき故意または過失によって違法に他人に損害を加えた場合において、国家賠償法1条1項により当該損害につき賠償責任を負うのは国であり、当該都道府県が賠償責任を負うことはない。 |
| スーパー答練3rd③行政法【問題11】肢4…○ 国家賠償法1条1項の「職務を行うについて」に該当するためには、公務員が主観的に権限行使の意思をもっていたことまでは必要でなく、公務員がもっぱら自己の利益を図る意図であった場合もこれに含まれるとするのが判例である。 |
本試験問題行政法【問題21】肢4…× 国家賠償法1条1項が定める「公務員が、その職務を行うについて」という要件につき、公務員が主観的に権限行使の意思をもってするものではなく、専ら自己の利をはかる意図をもってするような場合には、たとえ客観的に職務執行の外形をそなえる行為をした場合であったとしても、この要件には該当しない。 |
| スーパー答練1st行政法⑤【問題12】肢1…× 住民監査請求は、有権者総数の50分の1以上連署をもって、その代表者が監査委員に対して行わなければならない。 |
本試験問題行政法【問題23】肢1…○ 住民監査請求は、普通地方公共団体の住民が当該普通地方公共団体の監査委員に対して行う。 |
| 科目別答練行政法②【問題15】肢5…× 普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に、条例に違反した者に対し、刑罰を科す旨の規定を設けることができるが、法律の個別的授権を必要とする。 |
本試験問題行政法【問題24】肢2…× 普通地方公共団体は法令に違反しない限りにおいて条例を定めることができるが、条例において罰則を定めるためには、その旨を委任する個別の法令の定めが必要である。 |
| 総合答練③行政法【問題22】肢4…○ 普通地方公共団体の行政委員会は、法律の定めるところにより、法令または普通地方公共団体の条例もしくは規則に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則その他の規程を定めることができる。 |
本試験問題行政法【問題24】肢4…○ 普通地方公共団体の委員会は、個別の法律の定めるところにより、法令等に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則を定めることができる。 |
| スーパー答練1st行政法⑤【問題9】肢1…× 普通地方公共団体の執行機関としての委員会は、法律の定めがなくても、法令または普通地方公共団体の条例もしくは規則に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則その他の規程を定めることができる。 |
本試験問題行政法【問題24】肢4…○ 普通地方公共団体の委員会は、個別の法律の定めるところにより、法令等に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則を定めることができる。 |
| 全国公開模試②行政法【問題8】肢ウ…× …公立学校の施設の目的外使用を許可するか否かは、原則として、管理者の裁量に委ねられていると解するが、当該目的外使用を許可しても、学校教育上の支障がないと認められる場合には、管理者がこれを許可しなければならない。 |
本試験問題行政法【問題25】肢ウ…× 公立学校の学校施設の目的外使用を許可するか否かは、原則として、当該施設の管理者の裁量に委ねられており、学校教育上支障がない場合であっても、学校施設の目的及び用途と当該使用の目的、態様等との関係に配慮した合理的な裁量判断により許可をしないこともできる。 |
| スーパー答練1st基礎知識【問題17】肢4…○ 行政機関の職員が行政文書を作成または取得したときは、当該行政機関の長は、当該行政文書について分類し、名称を付するとともに、保存期間および保存期間の満了する日を設定しなければならない。 |
本試験問題行政法【問題26】肢3…○ 行政機関の職員が行政文書を作成・取得したときには、当該行政機関の長は、政令で定めるところにより、当該行政文書について分類し、名称を付するとともに、保存期間および保存期間の満了する日を設定しなければならない。 |
| スーパー答練1st基礎知識【問題17】肢5…○ 行政機関の長は、行政文書の管理が適正に行われることを確保するため、行政文書管理規則を設けなければならない。 |
本試験問題行政法【問題26】肢4…○ 行政機関の長は、行政文書の管理が公文書管理法の規定に基づき適正に行われることを確保するため、行政文書の管理に関する定め(行政文書管理規則)を設けなければならない。 |
| 総合答練②行政法【問題55】肢4…× 行政機関の長は、行政文書ファイル管理簿の記載状況その他の行政文書の管理の状況について、毎年度、内閣総理大臣に報告しなければならず、この報告を怠った場合は、2年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられる。 |
本試験問題行政法【問題26】肢5…○ 行政機関の長は、行政文書ファイル管理簿の記載状況その他の行政文書の管理の状況について、毎年度、内閣総理大臣に報告しなければならない。 |
商 法
| 2024年合格目標 TAC教材 | 令和6年度 行政書士本試験問題 |
|---|---|
| スーパー答練1st商法①【問題20】肢5…○ 会社が保有する自己株式については議決権が認められず、当該自己株式につき剰余金を配当することもできない。 |
本試験問題商法【問題37】肢イ…○ 株式会社は、自己株式については、議決権を有しない。 |
| スーパー答練1st商法②【問題9】肢4…× 取締役は、取締役会決議に特別の利害関係を有する場合であっても、当該取締役会の議決に加わることができる。 |
本試験問題商法【問題37】肢ウ…× 取締役候補者である株主は、自らの取締役選任決議について特別の利害関係を有する者として議決に加わることができない。 |
| ミニテスト商法④【問題2】肢3…× 監査役の選任・解任は、その職務の重要性に鑑み、株主総会の特別決議によってなされる。 |
本試験問題商法【問題37】肢エ…× 監査役を選任し、又は解任する株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。 |
| スーパー答練1st商法②【問題10】肢2…○ 監査役は、いつでも、株主総会の特別決議によって解任することができ、正当な理由なく解任された者は、株式会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。 |
本試験問題商法【問題37】肢エ…× 監査役を選任し、又は解任する株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。 |
| ミニテスト商法④【問題5】肢5…○ 取締役が任務を怠ったことにより負う会社に対する損害賠償責任は、総株主の同意により免除することができる。 |
本試験問題商法【問題37】肢オ…○ 役員等がその任務を怠ったために株式会社に生じた損害を賠償する責任を負うこととなった場合に、当該責任を免除するには、議決権のない株主を含めた総株主の同意がなければならない。 |
| スーパー答練3rd③【問題19】肢3…× 取締役が故意により任務を懈怠した場合、取締役の会社に対する損害賠償責任は、総株主の同意によっても免除することができない。 |
本試験問題商法【問題37】肢オ…○ 役員等がその任務を怠ったために株式会社に生じた損害を賠償する責任を負うこととなった場合に、当該責任を免除するには、議決権のない株主を含めた総株主の同意がなければならない。 |
| スーパー答練1st商法②【問題25】肢1…○ 株式交換とは、株式会社がその発行済株式の全部を他の株式会社または合同会社に取得させることである。 |
本試験問題商法【問題39】肢2…× 株式交換完全親会社は、株式交換完全子会社の発行済株式の一部のみを取得することとなる株式交換を行うことができる。 |
| スーパー答練1st商法②【問題4】肢ウ…× 株主総会の決議内容が法令に違反する場合には、株主総会決議取消しの訴えの対象となるが、株主総会の決議内容が定款に違反する場合には、株主総会決議無効確認の訴えの対象となる。 |
本試験問題商法【問題40】肢1…× 株主総会の決議の内容が法令に違反するときは、当該株主総会決議の日から3か月以内に、訴えをもってのみ当該決議の取消しを請求することができる。 |
| スーパー答練2nd商法【問題4】肢5…× 株式会社の設立の無効を主張するときは、株主、取締役、会社債権者が、会社成立の日から2年以内に、設立無効の訴えによってのみ行うことができる。 |
本試験問題商法【問題40】肢2…○ 会社の設立無効は、会社の成立の日から2年以内に、訴えをもってのみ主張できる。 |
基礎知識
| 2024年合格目標 TAC教材 | 令和6年度 行政書士本試験問題 |
|---|---|
| 科目別答練基礎知識【問題11】肢エ…○ 行政書士は、その事務所の見やすい場所に、その業務に関し受ける報酬の額を日本行政書士会連合会の定める様式に準じた表により掲示しなければならない。 |
本試験問題基礎知識【問題52】肢1…〇 行政書士は、その事務所の見やすい場所に、その業務に関し受ける報酬の額を掲示しなければならない。 |
| ミニテスト基礎知識④【問題2】肢2…○ 行政書士は、その事務所の見やすい場所に、その業務に関し受ける報酬の額を掲示しなければならない。 |
本試験問題基礎知識【問題52】肢1…〇 行政書士は、その事務所の見やすい場所に、その業務に関し受ける報酬の額を掲示しなければならない。 |
| スーパー答練1st基礎知識【問題11】肢3…○ 行政書士は、その事務所の見やすい場所に業務に関し受ける報酬の額を掲示しなければならず、依頼人の依頼しない書類を作成して報酬を受けてはならない。 |
本試験問題基礎知識【問題52】肢1…〇 行政書士は、その事務所の見やすい場所に、その業務に関し受ける報酬の額を掲示しなければならない。 |
| スーパー答練3rd③【問題24】肢1…○ 行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理する事務は、特定行政書士に限り、行うことができる。 |
本試験問題商法【問題52】肢2…× 行政書士は、自ら作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求について、その手続を代理することはできない。 |
| 科目別答練基礎知識【問題2】肢オ…× デジタル庁は、経済産業省の外局である。 |
本試験問題基礎知識【問題56】肢1…× デジタル庁は、総務省に置かれている。 |
| スーパー答練3rd②【問題26】肢2…× 個人情報取扱事業者は、その自ら取り扱う個人データの漏えい、滅失、毀損その他の個人データの安全の確保に係る事態が生じたときは、個人の権利利益を害するおそれの程度にかかわらず、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該事態が生じた旨を個人情報保護委員会に報告しなければならない。 |
本試験問題基礎知識【問題57】肢1…○ 個人情報取扱事業者は、個人データの漏えい等が発生し、個人の権利利益を害するおそれが大きい場合には、個人情報保護委員会への報告を行わなければならない。 |
| 総合答練③【問題57】肢5…× 学術研究機関等の個人情報等および個人関連情報を取り扱う目的の全部または一部が学術研究の用に供する目的であるときは、法第4章の規定は、適用しない。 |
本試験問題基礎知識【問題57】肢4…× 学術研究機関が学術研究目的で個人情報を取り扱う場合には、個人情報取扱事業者の義務に関する規定は適用されない。 |
| ミニテスト基礎知識⑥【問題5】肢ウ…× (「個人情報の保護に関する法律」)地方公共団体の機関(議会を除く)については、この法律の規律対象とはならない。 |
本試験問題基礎知識【問題57】肢5…○ 国の行政機関や地方公共団体の機関にも、個人情報保護法の規定は適用される。 |
| スーパー答練1st基礎知識【問題25】肢5…× 地方公共団体の機関(議会を除く)による個人情報の取り扱いは、各自治体が制定する個人情報保護条例の定めによる規律に委ねられ、個人情報保護法による規律を受けない。 |
本試験問題基礎知識【問題57】肢5…○ 国の行政機関や地方公共団体の機関にも、個人情報保護法の規定は適用される。 |