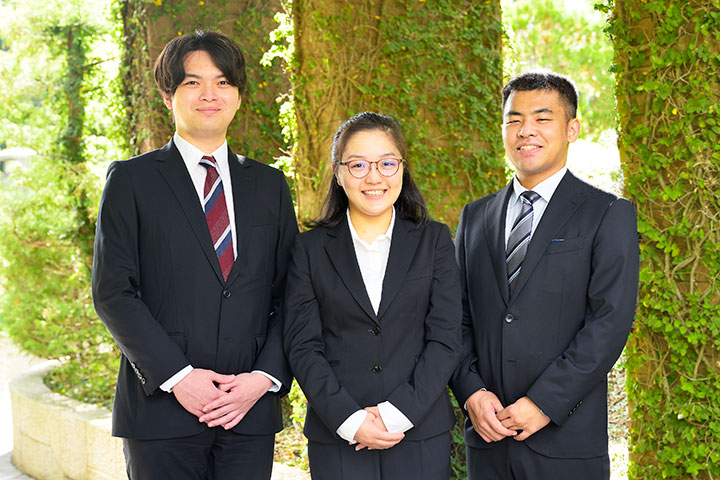特集 全盲の弁護士~どんな困難にも負けない男性の「諦めない生き方」

大胡田 誠(おおごだ まこと)氏
おおごだ法律事務所
代表弁護士
先天性緑内障により12歳で失明。慶應義塾大学大学院法務研究科(法科大学院)卒業。2006年司法試験合格、2007年渋谷シビック法律事務所入所。2012年に刊行した自著『全盲の僕が弁護士になった理由』(日経BP社)は松坂桃李主演のTVドラマになった。その後つくし総合法律事務所で企業法務など仕事の幅を広げ、2019年独立開業。幅広い法律事件に対応しつつ、障がい者など社会的マイノリティの支援をライフワークとする。私生活は全盲でシンガー・ソングライターの妻、一女一男、盲導犬の「4人+1匹」暮らし。趣味でマラソンを走る。
大胡田誠氏は全盲で司法試験に合格した日本で3人目の弁護士。先天性緑内障のため小学6年生で失明というハンディキャップを持ちながら、数々の工夫と努力で大学受験と司法試験を乗り越え、弁護士資格を手に入れた。アソシエイト(勤務弁護士)として12年の経験を積んだのちに「おおごだ法律事務所」を開設した彼は、障がい者を始めとするマイノリティが関わる事件の支援がライフワークだと語る。困難にぶつかっても「できない理由」は探さないという大胡田氏に、弁護士という資格の魅力とやりがい、そして諦めない心の持ち方についてうかがった。
修学旅行先の宿から見た最後の風景
──現在、弁護士としてご活躍中の大胡田さんが失明されたのは12歳の頃とうかがっています。
大胡田 そうですね。私の視力は小学校に上がった頃は0.1位ありましたが、先天性緑内障のために少しずつ低下していきました。
静岡県中伊豆町(現:伊豆市)で生まれたあとほどなく沼津市へ転居したのは、私と同じように視覚障がいを持って生まれた3歳年下の弟が沼津の盲学校に通うためでした。当時、私自身は地域の小学校で学んでいました。自分がいずれ視力を失うということは小さい頃から聞かされていましたが、現に今見えているものが目に映らなくなるということは、感覚的には理解できませんでした。小学6年生の修学旅行で名古屋へ行ったときのこと、夕食前の自由時間に私は旅館の窓から街並みを見ていました。夕陽が徐々に沈んでいくのを魅入られたように見ていた記憶があります。その後しばらくして私の目は見えなくなりましたので、名古屋の夕陽が視覚的な最後の景色だったと思います。
──多感な時期に、失明という事実を受け止めるのは難しくはありませんでしたか。
大胡田 そうですね。以前できていたことができなくなってしまう、歩くことが難しくなり本も読めないという中で、周囲の皆が自分をどう思っているかがとても気になりました。「かわいそうに」と思われているのかと思うと、それまで仲のよかった友だちとも距離ができたように感じました。自分が皆より劣った存在になってしまったようなコンプレックスを感じて、何とか学校へは行っていたものの、周囲から離れて自分の殻に引きこもるようになりました。その後、私は東京にある日本で唯一の国立の視覚特別支援学校である筑波大学付属盲学校(以下、筑波)へ進学したのですが、向上心があって筑波を選んだというよりは、目が見えなくなった自分を周りの人たちがどう見ているか気にしながら生活するのが苦しくなったからです。目が見えていた頃の自分を誰も知らない場所に行って一から始めたいという、逃げるような気持ちがありました。
そうして盲学校に入ると、授業には視覚障がいに配慮した様々な工夫があり、敷地内の寄宿舎での生活も楽しかった。周囲は小さい頃から全盲という学生が多くて、目が見えないなりの楽しみ方を知っているのです。バンドを組んで演奏したり休日に買い物へ出かけたり、皆いきいきと過ごしている。私も友だちと夜中に寮を抜け出して牛丼を食べに行ったことがあります(笑)。一緒にいろいろなことをやる中で、目が見えなくても楽しいことはあるのだということを知りました。気の合う仲間もできて、筑波での6年間は充実した時間だったと思います。
──筑波での様々な経験が、弁護士をめざすきっかけになったのでしょうか。
大胡田 きっかけは1冊の本です。中学2年生の夏休み、私は図書館で読書感想文の題材にするための本を探していました。背表紙の点字を探っていたとき、『ぶつかって、ぶつかって』(かもがわ出版)という題名が指に触れたのです。当時の自分は全盲になってまだ日も浅く、あちこちに頭をぶつけて、たんこぶが絶えない状況でした。また人生の壁にぶつかってしまったような思いもあったので、この題名に惹かれて読んでみることにしたのです。その本は、日本で初めて点字を使って司法試験に合格した竹下義樹弁護士の自伝でした。それまでの私は、失明したことで将来の可能性が閉ざされたと思っていたけれど、がんばって勉強すれば、弁護士という社会的責任の重い仕事にも就くことができるのだと知りました。目が見える友だちより劣った存在になったようなコンプレックスを持っていたけれど、弁護士になって困っている誰かのために働くことができたら、そんなコンプレックスからも自由になれるのではないかと思いました。
──14歳で弁護士になると心を決めてから、どのように受験勉強を進めたのでしょうか。
大胡田 筑波の高等部へ進み大学受験をめざしましたが、勉強したいと思っても参考書や問題集のほとんどは点字に対応していません。ですから大勢のボランティアの方々に、参考書を点字に翻訳してもらうことからのスタートでした。受験する大学を選ぶ段階でも、当時はまだ全盲の学生を受験させてくれる大学が限られていました。「今年は試験の準備が間に合わないので」とか「安全が保障できないので」とか、いろいろな理由で受験を認めてもらえない。それまで盲学校という守られた環境にいましたから、受験すらさせてもらえないという事実は、初めて経験した社会の荒波というか、これから生きていく社会の厳しさを感じさせられた出来事でした。
困った人へ手を差し伸べる弁護士に
──そうした困難を乗り越えて慶應義塾大学法学部に入学されましたが、大学生活はいかがでしたか。
大胡田 大学1年の春に、私にとって一生忘れられない出来事がありました。哲学の授業中、教授から「大胡田君、ちょっと荷物を持って前に来なさい」と言われたのです。何だろうと前へ出たところ、「君が点字でノートを取るときの音がうるさいと苦情が出ている。だから君は他の学生が座っていない、教室の端に座りなさい」と言われて。やっと大学に入って、ようやく皆と同じ学校で勉強ができると希望に胸を膨らませていた時期でしたから、教授の言葉が私にはとてもつらくて、思わず教卓の横で涙ぐんでしまいました。ところが次の瞬間に、教室のいたるところから私を弁護してくれるたくさんの学生の声が上がったのです。「同じ学生なのだから好きな所で授業を受ける権利がある」とか、「うるさいと思う人がいるなら、その人が動けばいいじゃないか」とか、そんな風に私を弁護してくれる声でした。それからは授業そっちのけで大討論会になり、最終的には「大胡田君は好きな場所で授業を受けていい、音がうるさいと思う人はその人が動きましょう」という結論になりました。この出来事は、障がいがあるが故に差別されてしまったというつらい経験でもありますが、同時に、自分を弁護し応援してくれる人の存在がどんなに勇気を与えてくれるか、差し伸べてくれる手がどんなに温かいかを身を持って知った経験でもありました。だから自分が弁護士になることができたら、差別を受けている人や周りから理解されずつらい思いをしている人のために働きたいと、そんな思いを抱くきっかけになりました。
──司法試験をめざす大きなモチベーションになりましたね。
大胡田 そうですね。とはいえ大学受験のときと同じく、司法試験の教科書や参考書は視覚障がい者には対応していませんでしたから、最初の頃はすごく困りました。ただ当時はすでにパソコンの画面読み上げソフトを使ってテキストデータを音読で聴けるようになっていましたので、司法試験の教材を電子データで提供してくれる受験指導校を見つけ、私の司法試験受験も可能性が見えてきました。
こう言うと大学時代はずっと勉強に専念していたように聞こえるかもしれませんが、実はそうでもありません。ボランティアサークルに入って、児童養護施設の子ども達に勉強を教えたり一緒に遊んだりするボランティアをやりました。普段私はボランティアの方々にお世話になることが多かったので、自分でも何か人のためにできることをしたいと思ったのです。そのサークル仲間とは、一緒にスキーをしたり夏は海に行ったりもしましたし、個人的にですがスキューバダイビングの資格も取りました。多くの経験をした大学時代でしたが、そのぶん司法試験の勉強が遅れてしまって、大学4年に初めて受けた試験の結果は惨憺たるものでした。当時の司法試験の短答式試験で、自己採点した点数が合格点の半分にも届かないという、箸にも棒にもかからない状態でしたね。

迷ったときは、自分の心が温かいと感じるほうを選ぶ
──大学卒業後は沼津のご実家へ戻って司法試験の勉強をされていたそうですが、どのような生活でしたか。
大胡田 沼津の実家で丸3年間受験勉強をしたのですが、最初は誰とも会わずに、ずっと「ステイホーム」みたいな生活でした。周囲には就職したり結婚したりする友人もいる中、自分だけ黙々と、いつ合格できるかわからない司法試験の勉強を続ける状況は、孤独で苦しかったです。
──どのようにしてモチベーションを保ったのですか。
大胡田 家にばかりいては煮詰まってしまうので、興味のあることがあれば出かけるようにしました。英会話やギター、カウンセリング講座、犯罪被害者支援のボランティア講習も受けました。外へ出て刺激を受けることを求めていたのだと思います。犯罪被害者支援のボランティアやカウンセリングは現在の仕事に直結していますから、よい経験だったと思いますね。でも司法試験にはなかなか受からない。当初は自分の中で、3回までは受験しようと思っていたのです。でもかなわずに、「本当に今度こそ」と受けた4回目も不合格。そうなると、この先どうしたらいいかわからなくなってしまいましたね。
受験生時代、我が家には毎年恒例の儀式がありました。それは5月の短答式試験が不合格になると、両親の前に正座して「お父さんお母さん今年も駄目でした。もう1年勉強させてください」とお願いする儀式です。4回目が不合格だったときも両親の前に正座したのですが、もう1年やらせてほしいという言葉がなかなか言えなくて、「どうしたらいいかわからない、やめるべきかもしれない」と言いました。すると母が「迷ったときには自分の心が温かいと感じるほうを選びなさい」と言ってくれたのです。それで私ももう一度、自分の心に問いかけてみました。つらい受験勉強をまた1年がんばれるか、そこまでして弁護士になりたい気持ちがあるのかと考えたときに、まだ弁護士になりたい気持ちが残っていたのですね。弁護士になって困っている誰かを助ける、弁護士バッヂをつけて裁判所の中を闊歩する自分を想像すると、心が温かくなったのです。まだ燃えている気持ちがあると感じたので「もう一度がんばろう」と決めました。結局何かに迷ったときは、他人からどう思われるとか、どちらが得か損かということではなく、「自分の心が何を求めているか」ということが答えなのだと思います。それを母は「心が温かいと感じるほう」と表現したのでしょうね。
「耳で受験」を可能にするために
──受験を続けることを決め、2004年、慶應義塾大学大学院法務研究科へ入学したのですね。
大胡田 ちょうどこの頃、ロースクール制度ができたのです。法科大学院に入って、また2年間勉強することになりましたが、ただガムシャラに司法試験の勉強をするより、つらくてもゴールに近づくロースクールのほうが自分に合っていると思いました。でもロースクールができたばかりで教授の方々も気合いが入っていましたし、指導は厳しかったですね。1コマに必要な資料として判例を100ページも読んで来るのが前提という授業が、毎日3~4コマありました。資料は当然プリントで渡されますから、自分でスキャナーを買って資料を取り込み、文字認識ソフトでテキストに変換して読んでいくのです。この作業に夜中の3時位までかかりましたので、夜通し作業して授業中に寝てしまうようなことも多々ありました。すると、大学院のほうで視覚障がいの学生の勉強に協力できるボランティアの募集をかけてくれて、4人の学生が手を挙げてくれました。自分も勉強が大変なはずなのに、私の教材づくりや予習をサポートしてくれて、本当にありがたかったです。
──大学院在学中には、法務省と掛け合って受験方法を変えてもらったそうですね。
大胡田 ええそうです。新制度の司法試験は資料を読んで自分の主張を組み立てるという論述問題が多く、資料が膨大な量になります。点字で読んでいたのではとても間に合わないので、パソコンを使って音声で問題を聞き、電子データで解答できるようにしてほしいと法務省へ申し入れをしました。法務省側でも誠実に対応していただいて、パソコンを使って耳で受験することが可能になりました。
意外と知られていないことですが、実は視覚障がい者のうち点字をスラスラ読める人は全体の10%程度なのです。私のような中途失明ですと、点字をまったく読めない人も多い。この意味で、パソコンを使って耳で司法試験が受けられるようになったのは、点字の読めない視覚障がい者にとっても、大きな成果だったと思います。
──司法試験に向けて他にも工夫されたことはありましたか。
大胡田 司法試験は何日もかけて行われる長大な試験ですから、最後まで戦い続ける体力が必要です。私は在学中から週1回、プールで2㎞泳いで体力をつけるようにしました。ロースクール修了後は、1日を試験と同じタイムスケジュールで生活しました。試験開始時間から勉強をスタートして1時間の昼休みをはさみ、13時から再開というふうに、試験時間の感覚を身体に染み込ませたのです。
──生活スタイルも司法試験に合わせていたのですね。
大胡田 はい。そうして準備した試験でしたが、行政法の試験のときに背筋が凍る瞬間がありました。道路の設置許可に関する問題でしたが、参考資料の点図(点字で表現した地図)がまったく把握できないのです。問題が解けない以前に地図を読めずに終わってしまうかもしれないという思いに襲われゾッとしました。そこでいったん中座してトイレにこもり、自分を支えてくれた人たちや当時はまだ恋人だった妻の声を懸命に思い出しました。試験中に心が折れそうになったときはそうしようと、前もって決めていたのです。皆の声を思い出していると、心に芯が通るような瞬間があって「がんばろう」という気になりましたね。そうして席に戻りもう一度点図を探ったところ、何とか手がかりが見つかり、解答することができました。そして運命の合格発表は2006年9月21日、私は法務省へひとりで行きました。自分では掲示板の番号を見ることができないので、近くの警備員さんに受験票を渡して番号を見てもらいました。「ありましたよ、おめでとう!」と言われたときは、涙が止まりませんでしたね。

障がいを持った弁護士であるからこその強み
──合格後、司法修習を終えて初めての職場となった渋谷シビック法律事務所は、どのような職場でしたか。
大胡田 渋谷シビック法律事務所は、第一東京弁護士会が設立した公設事務所です。経済的に弁護士を雇う余裕がない方の弁護も引き受けるので、「最後のセーフティネット」とも言われます。それと同時に新人弁護士の養成機関でもあります。私はここで6年間、弁護士として働かせてもらいました。
忘れられないのは弁護士になって半年ほどのときに、当時の所長の齊藤先生から言われた言葉です。たまたまふたりだけで食事をする機会があったので、「先生はどうして私のことを雇ってくれたのですか?」と聞いてみたのです。すると齊藤先生はさらりと「それが事務所と依頼者のメリットになると思ったからだよ」とおっしゃいました。私を雇うことでパソコンの画面読み上げソフトや点字プリンターなど専用の設備を整えなければいけませんし、アシスタントを雇うなど経済的負担もあったはずなのに、私という弁護士を雇うことをメリットと言ってくれたことが本当にうれしかったです。
──特に記憶に残っている事件などはありますか。
大胡田 当時扱った事件の中では、連続万引き犯の弁護が記憶に残っています。彼は足が不自由だったためになかなか定職に就けず、万引きした商品を売って生活していたのです。私は国選弁護人として彼の弁護をしたのですが、結局実刑になりました。その彼が刑務所の中から私に手紙をくれたのです。そこには「先生にとてもお世話になったので、自分は今、点字の勉強を始めています。社会に戻ることがあったら、今度は点字の知識を使って自分が先生の役に立ちたいです」と書かれていました。私の目が見えないことが、彼に対して言外に前向きなメッセージを伝えたのかもしれないと思うと、うれしかったですね。
──その後、弁護士をめざすきっかけになった本の著者である竹下義樹弁護士が代表を務めるつくし法律事務所へ入所されました。
大胡田 竹下先生に初めてお会いしたのは、大学1年の春休みでした。私が法曹をめざすきっかけとなった憧れの先生ですから、司法試験に挑戦するにあたり、どうしても会っておきたくて、連絡を取って京都の事務所まで会いに行ったのです。先生は自信に満ち溢れて、何人ものスタッフに指示を飛ばし、事務所全体を動かしていました。その先生が新しく東京に事務所を開いたので、これはどうしても修行させてもらいたいと、お願いして入れてもらいました。
つくし法律事務所は企業法務など多様な事件を扱う法律事務所で、私も企業法務や医療過誤事件など、様々な事件を担当させてもらいました。また竹下弁護士の仕事への向き合い方というか、仕事への姿勢を肌で経験することができたことは今も財産になっています。
──この間に大胡田さんご自身の自伝『全盲の僕が弁護士になった理由』が、松坂桃李さん主演でTVドラマになりましたが、仕事面で反響はありましたか。
大胡田 ありましたね。様々な依頼をいただくきっかけになりましたし、「松坂さんのような恰好良い弁護士が出て来ると期待して来たのに…」みたいな反応もありました(笑)。
──2019年におおごだ法律事務所を設立されましたが、独立した理由を教えて下さい。
大胡田 竹下先生が「そろそろ独立したらどうだ?」と言ってくださったのです。先生のことですから、それは私のためを思っての言葉だと思います。「自立した弁護士であれ」ということですね。
私の事務所では債務整理、交通事故、遺産相続などの案件の他に企業法務も取り扱っています。またライフワークとして、障がい者をはじめとするマイノリティが関わる事件の支援もやっています。例えば最近の事件では、視覚障がいを持つ少女が交通事故に遭った事件の控訴審裁判を手掛けています。一審の判決で、この被害者の遺失利益(事故に遭ったために生涯で得られなくなった利益)は「健常者の7割」という判決が出ましたが、私は「これはおかしい」と思います。現在はいろいろなサポートがあって、障がいがあっても働ける環境になっているのですから。
──大胡田さんが弁護すること自体がその証拠になりますね。
大胡田 そういうことだと思います。視覚障がいがあっても、弁護士として自立し、しっかり生計を立てられるという事実を、裁判官に見てもらえることは意味があると思っています。これまで障がいを持つ年少者の事故で、健常者と同等の遺失利益を認めた判例はなかったと思いますが、その前例をひとつでも変えられたらという願い、そして少しでも社会を変えたいという思いがありました。
仕事のクオリティを上げるダブルライセンス
──2019年の開業後まもなくコロナ禍になりましたが、この間にまた別の資格も取られたそうですね。
大胡田 もっと多様な相談に対応したいと思い、キャリアコンサルタントの資格を取りました。困っている人の助けになりたいというのが弁護士になった大きな理由ですが、弁護士のところに来る相談はどうしても何らかの法律問題になります。私は法律に限定せず、様々な人生のお悩みを聞かせてもらえる立場になりたかったのです。実際に、顧問先の企業で、悩みを抱える社員のサポートをするようになりました。相談の間口が広がって法律顧問から一歩深いサポートができるようになり、仕事のクオリティが上がったと思います。今後は様々な問題を抱えた方のご相談に乗って精神的にもサポートできるような、もちろん法的知識も提供できるような、幅広さと深みのある仕事をしていくのが目標です。
「できない理由」ではなく「できる方法」を探す
──困難にあったとき、どのようなマインドセットで乗り越えていけばよいでしょうか。
大胡田 「できない理由」を探すのではなく「できる方法」を探すということですね。人間は、自分の探しているものしか見つけない性質があると思います。困難にぶつかったとき、できない理由を探せば、簡単に見つかります。目が見えないから無理、とかね。でもそこで踏み留まってできる方法を探せば、それも大抵の場合、見つかるのです。できる方法を探そうと思えるかどうかが、人生の分かれ目だと思います。また壁だけを見ずに、この壁を超えたらどれだけ楽しいことがあるのかをポジティブに考えるほうがいいと思います。一生懸命に楽しそうにがんばっていれば、サポートしてくれる人もきっと出てきます。妻は私のことを「あなたは目が見えない障がいじゃなくて、できないことが見えない障がいだ」と言います。資格試験の勉強に限らず、何か夢や目標に向かって進んでいく中では壁にぶつかることもあると思いますが、壁を超える方法はひとつではありませんし、きっと他の方法も見つかるはずです。ぜひ探してみて、夢や目標を叶えてほしいと思います。
[『TACNEWS』 2021年8月号|特集]