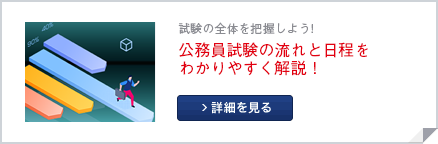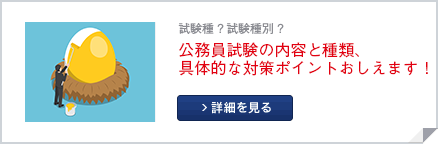公務員試験 併願受験はやらなきゃ損!知っておくべきポイントは?

公務員試験は併願受験が可能です。「本命1社しか受けません」という人がほとんどいないような、民間企業と同様の就職試験だといえます。今回は、併願受験の4つのメリットについて解説。注意点も踏まえながら、公務員試験の戦略を立てていきましょう。
公務員 地方上級・市役所・国家一般職 デジタルパンフレットを閲覧する
公務員試験対策ならTAC!
公務員試験の併願戦略
日程が違えばいくつでも併願できる!

公務員試験は年齢等の受験資格さえ満たしていれば、1次試験日が重なっていなければいくつでも併願受験が可能です。
併願受験の例 ※2024年度(行政事務職)の場合
公務員試験は、民間企業との併願も可能です。併願すれば、公務員のみ、民間のみに限られた就職活動と比べ、選択肢の幅が広がります。
併願の際は、公務員の職種に関連する企業を志望するのがおすすめです。志望動機や自己PRなどを複数作成する手間が省けます。併願する業界を絞り込むことで、自然と公務員試験対策に通ずる道筋が見えてくるでしょう。
公務員試験の日程表(1次試験)↓↓
数ある公務員試験の中でも、地方上級(都道府県・政令指定都市)や国家公務員は、例年ある程度の採用人数が見込める試験種です。
より確実に合格を目指すために、C日程(9月実施)の市役所が第一志望という方も、できる限り5~6月に実施される地方上級や国家公務員を受験先として考えておくことをおすすめします。
併願時のポイント①
- 多くの合格者が万が一のリスクを回避するべく、3~6つ程度の試験種を併願受験している
併願受験の例 ※2024年度(行政事務職)の場合
| パターン | 併願受験する試験種 |
|---|---|
| 幅広く併願 | 国家総合職、特別区Ⅰ類or東京都Ⅰ類B、裁判所一般職(大卒)、国税専門官or財務専門官or労働基準監督官、 国家一般職(大卒)、地方上級(県・政令指定都市)、国立大学法人等、市役所B日程、市役所C日程、独自日程の市役所 |
| 地方公務員のみで併願 | 特別区Ⅰ類or東京都Ⅰ類B、地方上級(県・政令指定都市)、市役所B日程、市役所C日程、独自日程の市役所 |
| 国家公務員のみの併願 | 国家総合職、裁判所一般職(大卒)、国税専門官or財務専門官or労働基準監督官、国家一般職(大卒) |
| 教養試験のみで併願 | 東京都Ⅰ類B(新方式)、市役所A日程、市役所B日程、国立大学法人等、市役所C日程、独自日程の市役所 |
公務員試験を併願する4つのメリット
公務員試験を併願するメリットとして挙げられるのは、以下の4点です。
- リスク分散
- 本命受験前の練習になる
- プレッシャーが軽減される
- 本番の様子がわかる
複数の試験を併願すれば、本命受験の前に試験のイメージをつかめます。ひとつの試験のみにかかるプレッシャーも軽減されるでしょう。それぞれのメリットを参考に、併願受験に向けて前向きに検討してみてください。
1.リスク分散
公務員試験も就職試験であり、就職・転職活動でもあります。特にこれから就職する方は、複数の試験を併願すれば内定獲得の可能性が高まっていきます。
2.本命受験前の練習になる
併願先の受験は、本命受験の前の練習になることがあります。公務員試験の出題内容は、全体的に似た傾向にあるからです。また、併願受験をすると、その年の出題傾向が見えることもあり、本命受験に生かせることもできます。
時期の早い国家公務員総合職試験を併願すれば、その後の国家公務員一般職試験や地方公務員試験において大きなメリットとなるでしょう。
3.プレッシャーが軽減される
受験先を1本のみに絞ると、そこにかかるプレッシャーは大きくなるものです。必ず合格しなければという意気込みが、本番でマイナスに働く可能性があります。
併願先が多いほど、本命にかかるプレッシャーを軽減できます。希望先に必ず合格したいという熱意はもちろん大切ですが、試験対策のひとつとして併願も検討してみてください。
4.本番の様子がわかる
試験を受験することで、本番の様子がよくわかるというメリットもあります。当日の会場の様子を感じ取ったり、問題を解く時間配分などを掴めることができるでしょう。
また人物試験では、何が聞かれるのか?どんな雰囲気かを経験することで、試験に慣れることもできるでしょう。
公務員試験併願時の4つの注意点
公務員試験を併願する際は、以下の4点に注意してください。
- 日程かぶりを防ぐ
- 自分のキャパを越えない併願数を
- 優先順位をつけて勉強スケジュールを組む
- 試験情報は効率的に探す
これらに気を付けることで、前述したような併願のメリットを最大限に活かすことができます。日程やスケジュールについて悩むときは、公務員試験を専門とするスクールに相談するのもひとつの方法です。
1.日程かぶりを防ぐ
併願先の日程は、必ずしっかりと確認しましょう。誤って試験日がかぶることがないよう、試験情報は最新のものをチェックしてください。
友人や先生など、自分以外の信頼できる人に確認してもらうのもおすすめです。自分では気づかないミスも、第三者の目であれば発見できます。思いがけない間違いをしないよう、日頃から周囲の人と情報共有するように努めましょう。
2.自分のキャパを越えない併願数を
併願受験は本番前の練習になりますが、1つ1つの負担が大きいことに変わりはありません。あれもこれもと受験しキャパオーバーにならないよう、併願先を増やしすぎないよう気を付けましょう。
あくまでも本命に焦点を当てつつ、併願先を見極めることが大切です。長距離移動といったコストなども負担にならないように注意してください。
3.優先順位をつけて勉強スケジュールを組む
併願受験のための勉強スケジュールは、優先順位をつけて組み立てましょう。公務員試験は、教養科目から専門分野まで出題内容が幅広い試験です。本命に合格するためには、必要な範囲を取捨選択し、効率的に学習に取り組む必要があります。
特に、出題数の多い重要な科目は、本命合格の可能性を高めるためにも、優先的に学習を進めるよう心がけてください。
4.試験情報は効率的に探す
併願のために必要な試験情報は、効率的に探しましょう。特に、地方公務員の場合は試験情報が各自治体のWEBサイトに散らばっています。情報収集だけで時間がとられることも少なくありません。
間違いのない情報を効率的に得るには、公務員試験を専門とするスクールの情報をチェックするのがおすすめです。スクールを受講していれば、効率的な勉強法や日程の組み方なども相談できます。
出題科目・傾向で併願先を決める!
試験種ごとの試験区分表(行政事務)

東京都・裁判所一般職(大卒)・国家専門職などにおいては専門記述試験が課されますが、多くの公務員試験は、教養択一(基礎能力)試験+専門択一試験+論文試験という構成になっています。したがって、この3つの試験種目の対策を講じることで、幅広く併願しやすくなります。
市役所(教養型)や国立大学法人等、専門試験が課されない試験種も一部存在しますが、採用人数が例年それほど多くなく倍率が高くなる傾向にありますので、確保できる学習時間が極端に少なくない場合は、専門試験対策を含めた受験対策をしておくことをおすすめします。
併願時のポイント②
- 教養+専門+論文対策をしておくと、幅広く併願受験がしやすい!
- 社会人など、学習時間の確保が難しい場合は、教養試験のみでの併願も可能。ただし倍率が高くなりがちなので慎重な判断が必要
地方上級・国家一般職試験の対策・勉強法・攻略について詳しくはこちら
仕事の内容ももちろん大事です
ひとくちに「公務員」といっても、いろいろな職種があります。
国家公務員の中にも経済産業省や厚生労働省などの省庁で働くいわゆる「官僚」と呼ばれる国家総合職。
同じ省庁でも総合職を支える国家一般職、専門分野のスペシャリストである国税専門官や外務専門官などがあり、地方公務員の中にも都道府県の職員から市町村の職員など、仕事の内容もスケールもそれぞれです。
併願受験を考える際に、ある程度「やりたい仕事」を意識した受験先を選択することも必要です。
しかし、1次試験の日程が異なっていても2次試験、3次試験と選考が進むうちに面接の日程が重複してしまうこともあり、おのずと志望度の高い試験種を選択せざるを得ないタイミングは訪れますので、学習をスタートするタイミングではあまり難しく考えずに「できる限り併願受験をしよう」という姿勢で大丈夫です。
併願時のポイント③
- 選考が進むと、日程が重複することも出てくる。できる限り併願する姿勢が重要。